先般の良い食品づくりフォーラム信越は、87名の出席のもと大変充実した内容で終わることができました。

井出民生会長
恒例のセミナーでは、女子栄養大学副学長の五明紀春先生に、食品の風味や色を決定づける食品加工において最も重要な化学反応である「メイラード反応」についてご講演をいただきました。
東京大学名誉教授、農山漁村文化協会会長の今村奈良臣先生には、「地域活性化に向けた新事業創出〜人を生かす、資源を生かす、地域を興す〜」をテーマに、先生のこれまで経験されたことをもとに、本会が発展していくためにはどうすべきかを熱くお話いただきました。

女子栄養大学副学長 五明紀春先生

東京大学名誉教授、農山漁村文化協会会長 今村奈良臣先生
また、日本一の長寿県である長野での開催にちなんで地元で活躍されている信州郷土料理の研究家、横山タカ子先生をお招きし、長寿を支える食の知恵を学びました。

地元長野市在住の料理研究家、横山タカ子先生
生産者会員報告① 杉田味噌醸造場 杉田貴子さん

杉田味噌のある上越市は、江戸初期に開かれた城下町高田が核となっており、上方文化と江戸の文化が交錯して独特の食文化が築かれました。この地の味噌は米麹の配合量が多く、湯に溶くとこうじが浮く「浮き糀」が特徴であり、製糀工程に最も力を注いでいるとのお話でした。また、原料の大豆には地元新潟産を使用しており、生産から選別まで農家の方と一緒になって取り組んでいるそうです。県の大豆栽培技術、品質の向上に少しでもつながればと語られ、地元に貢献したいという思いが強く印象に残りました。
生産者会員報告② 村田商店 村田滋さん

地産地消にこだわり、県産大豆の使用を続けてきましたが、先日当社の製品をお買い上げていただいたお客様から「黒ずんだ大豆が目立っている」とのお叱りの連絡がありました。しかしながら、これは曲がったキューリ同様、見た目の問題であり、品質にはなんら問題はありません。これまで納豆作りを通じて県内の農業を応援したいという思いがあり、目をつむってきた部分を改めて考え直すきっかけとなりましたとお話されました。製品の「品質」の追求について重要な問題提起であり、一方で、消費者への啓蒙活動の必要性を感じざるを得ませんでした。
協力店会員報告① ボンラパス 柿原宏さん

「ボンラパス」とは、フランス語で「ごちそうさま」の意。他社で扱っていないオンリーワンの商品、オリジナル惣菜の開発、時間帯に応じた商品の展開等に力を入れているそうです。発表を通して、品揃えの良さが評判であり、地元の方に愛されている様子が伺えました。
協力店会員報告② 加島屋 後藤麻美さん

人口81万人、日本海側発の政令指定都市である新潟市の加島屋さん。発表を伺うと、ネットならではのオリジナル商品の販売や本店でのうまいもの市の開催、また児童の絵画展の企画・開催等、幅広く活動しておられる様子が分かりました。また、茶屋長作ではソフトクリームのコーンも店内で手焼きしており、安心・安全な食品づくりへの徹底した姿勢に心を打たれました。
会員の相互研鑽の場である「 良い食品づくりフォーラム」。
9月8日から10日までの3日間、長野ホテル犀北館を会場に下記プログラムを行い、無事終了することができました。
幹事役の地区会員の皆様をはじめ、全国からご参加くださった会員の皆様、お疲れさまでした。

〈実施プログラム〉
9月8日(日)
原材料製法部会/表示包装衛生部会/官能部会
部会終了後、合同研修
9月9日(月)
講演「メイラード反応の世界」女子栄養大学副学長 五明紀春先生
講演「地域活性化に向けた新事業創出〜人を生かす、資源を生かす、地域を興す〜」東京大学名誉教授・(社)農山漁村文化協会会長 今村奈良臣先生
生産者会員報告① 杉田味噌醸造場 杉田貴子さん
生産者会員報告② 村田商店 村田滋さん
講話「日本一の長寿県 長野の食」料理研究家 横山タカ子先生
9月10日(火)
協力店会員報告① ボンラパス 柿原宏さん
協力店会員報告② 加島屋 後藤麻美さん
「食品を識る」(各部会報告)
会員工場見学(杉田味噌醸造場、高橋孫左衛門商店)
先般の良い食品づくりフォーラム東北は、歴史に残る東日本大震災の被災現地で開催しました。
98名の会員が参加し、深い学びの内容に満ちていました。
恒例のセミナーでは、建築家・妹島和世建築設計事務所代表の妹島和世先生をお迎えしました。
「環境と建築」と題し、これまで手がけてこられた街づくりについてお話をいただきました。
また、被災地で進められている復興支援プロジェクト「みんなの家」についても、被災地の現状や地元の方との交流を通して感じることなどを交えながら、ご説明いただきました。
自然栽培農家木村秋則先生には、「奇跡のリンゴが実るまで」と題し、無農薬りんごへのチャレンジとその精神について語っていただきました。

生産者会員報告① キープ協会

キープ協会の名前は「Kiyosato Education Experiment Project」の頭文字をとったもの。ポールラッシュ博士によって戦後日本の民主的な農山村復興モデルをつくることと、実践的な青少年教育を目的に創設されたという歴史から、現在力を入れて取り組んでいる環境教育(酪農、搾乳体験等)まで分かりやすくスピーチいただいた。教育において知ることよりも感じることの大切さを強く感じました。
生産者会員報告② 西出水産 西出隆一さん

江戸初期にさんま漁を初めて行ったのは和歌山の漁師だったそうで、和歌山の食文化に「さんま」は欠かせないそうです。創業から50年、和歌山市の雑賀崎で灰干さんまを作り続けている西出水産の西出社長には、原材料や製法のこだわり、品質を向上させるための努力等についてお話をいただきました。中央市場の競りの仕事に携わっていたが、30歳の時にこの伝統を自分が残していかねばと思い、家業を継いだというエピソードに強く心を打たれました。
協力店会員報告① 良い食品處さとなか 里仲純二さん

「良い食品處さとなか」は、「古事記」の編纂に関わった語り部の祖・稗田阿礼の出身地である奈良県大和郡山市にあることにちなんで、昨年から「食の語り部」講座を定期的に開催されています。これまでの講座の内容や参加者の反応などをご説明いただいた後、この講座を通して、素晴らしい日本の食文化を次代に伝えていきたいとの思いを語られました。
協力店会員報告② ペント 中島理晴さん

本会会員・丸八製茶場のお茶に出合いそのおいしさに感動したことが、入会のきっかけになったというペント中島さん。会の勉強会に誘われて初めて参加した時は、自身の知識の足りなさを実感したそうです。それから3年程、勉強会に通い続けてやっと入会が認められ、2010年晴れて会員となったそうです。このスピーチでは、徹底したコスト管理やチラシ作りの工夫、それから「モノを売るからコトを売ること」「社是は従業員を幸せにすること」など、自身の哲学を熱く語られました。
講話「大震災から復興へ」
「宮城県女将会」磯田悠子会長と仙台に拠点を置く会員から、当時の被災状況やその体験から学んだこと、そして復興状況についてお話いただきました。
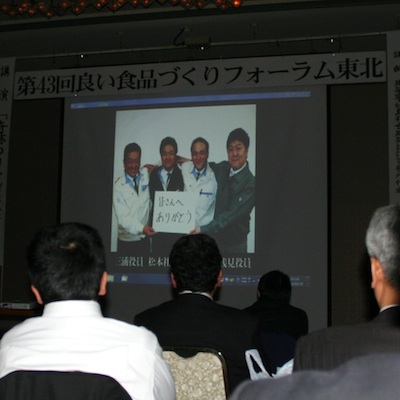



一ノ蔵 鈴木整さん(左上)、宮城県女将会会長 磯田悠子様(右上)
精華堂あられ総本舗 清水敬太さん(左下)、仙台味噌醤油 佐々木淳一郎さん(右下)
会員の相互研鑽の場である「 良い食品づくりフォーラム」。
今回は宮城県松島で下記のプログラムを行い、無事終了することができました。
幹事役の東北地区会員の皆様をはじめ、全国からご参加くださった会員の皆様、お疲れさまでした。
〈実施プログラム〉
2月17日(日)
原材料製法部会/表示包装衛生部会/官能部会
部会終了後、合同研修
2月18日(月)
講演「環境と建築」建築家・妹島和世建築設計事務所代表 妹島和世先生
講演「奇跡のリンゴが実るまで」自然栽培農家 木村秋則先生
生産者会員報告① キープ協会
生産者会員報告② 西出水産 西出隆一さん
講話「大震災から復興へ」
宮城県女将会会長 磯田悠子様
仙台味噌醤油 佐々木淳一郎さん
精華堂あられ総本舗 清水敬太さん
一ノ蔵 鈴木整さん
2月19日(火)
協力店会員報告① 良い食品處さとなか 里中純二さん
協力店会員報告② ペント 中島理晴さん
「食品を識る」(各部会報告)
被災地見学(石巻の被災地、復興仮設商店街の現状を視察)
9月10、11日の2日間、「第42回良い食品づくりフォーラム東京」を開催し、
104名の出席のもと、大変充実した内容で終わることができました。
恒例のセミナーでは、国立民族学博物館名誉教授の石毛直道先生をお迎えし、
「世界にひろがる日本食」をテーマにご講演をいただきました。
また、元京都大学原子炉実験所助教授の海老澤徹先生には、
最新データに基づいて「福島原発事故と食品汚染の現状」をご説明いただいた後、
会員それぞれが扱う食品の放射能汚染状況や、それに対する対応について、
個別にアドバイスいただきました。

会の冒頭で井出会長が挨拶しました
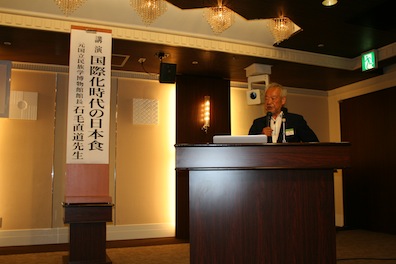
石毛直道先生講演「世界にひろがる日本食」

海老澤徹先生講演「福島原発事故と食品汚染の現状」
[会員報告レポート]

「うちは『菓子屋』」よりも『栗屋』」 桜井甘精堂 桜井昌季さん
栗はデリケートな果物で、すぐに変色し、手をかければかける程、風味がなくなると言います。
おいしい栗菓子づくりのため、製法はできるだけシンプルに。機械化して商品の味が変わっては
本末転倒、安易な効率化は行わない等、桜井甘精堂の素材の風味を第一に考える姿勢に共感しました。

「ものづくりは、人の手から離れてはいけない」久保食品 久保隆則さん
添加物を使わない豆腐づくりを志したきっかけ、本会入会の経緯をお話いただいた後、
会の理念に沿ってお店の取り組みを丁寧に説明いただきました。「いいものは人から生まれる。
ものづくりは人の手から決して離れてはいけない」という言葉が強く心に響きました。

「この会が持つ本質感を若い視点で伝えるために」D&DEPARTMENT 相馬夕輝さん
「デザインとは、パッケージなど表層のことだけではなく、何よりまっとうなものづくりがあって、
その上に、それをいかに背景や姿勢、ビジョンを伝え、販売するかということである。」
普段はあまり馴染みのない「デザイン」について考える貴重な機会となりました。
また、d勉強の会の実施や渋谷ヒカリエ内「d47食堂」で会の製品を使った定食メニューの提供等、
販売協力店としての活動についてもお話いただきました。

認定品売り場の工夫 近鉄百貨店奈良店 パントリー 安食達也さん
近鉄百貨店奈良店における認定品売場の工夫についてご説明いただきました。
会についての説明ボードを一新し、POPを作って商品や生産者について分かりやすく伝えたり、
「良い食品フェア」を行う等、会を積極的にアピールされており、その熱意にたいへん刺激を受けました。

良い食品博覧会をPR ラッキーやまと小泉店 岩本範久さん
第一回大和郡山 良い食品博覧会のPRについての取り組みについて説明いただきました。
博覧会に興味を持ってもらうため、食品サンプルを使ったり、分かりやすいポップを作ったりと、
様々な工夫をされており、たいへん参考になりました。また、今年5月から毎月開催している
「食の語り部」講座についての様子やお客様の反応についてもお話しいただきました。
